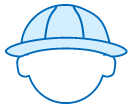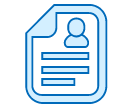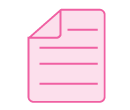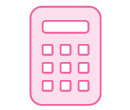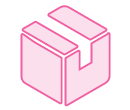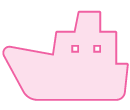更新日:2025年2月6日
ここから本文です。
子宮頸がん予防ワクチン
子宮頸がん予防ワクチンは、「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン」とも言います。
まだ間に合いますキャッチアップ接種
これまで接種機会を逃した方にキャッチアップ接種として令和7年3月末まで定期接種として取り扱うこととしていましたが、このたび、令和4年4月1日から令和7年3月末日までに少なくとも1回以上接種していることを条件に、2回目及び3回目の接種費用が無料となる期間を令和8年3月末日まで延長することが決定されました。公費による接種を希望される方は1回目の接種を令和7年3月末までに行うことをご検討ください。
目次
子宮頸がん予防ワクチンの予防接種とは
予防する病気
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
子宮頸がん予防ワクチン予防接種の詳しい情報
次のリーフレット等を参考に、ワクチンの有効性や副反応等について医師とよく相談し、接種を検討してください。
- 9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(定期接種版)_2024改訂(PDF:604KB)
- HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(概要版)_2025年2月改訂版(PDF:5,197KB)
- HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(詳細版)_2025年2月改訂版(PDF:6,361KB)
- 厚生労働省HP(外部サイトへ別ウィンドウで開きます)
対象者
小学6年生~高校1年生の女の子
小学6年生の女の子には中学1年生時に発送します。希望者は今年度接種することも可能です。
平成9年度生まれ~平成19年度生まれの女性(キャッチアップ接種対象者)
積極的な勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方
ワクチン種類と接種回数等
公費で接種できる子宮頸がん予防ワクチンは、3種類です。
(1)2価ワクチン:サーバリックスを接種する(3回接種)
- 1回目の接種をしてから1月の間隔をおいて2回目を接種し、1回目の接種から6月の間隔をおいて3回目を接種。
- ただし、やむを得ず上記のとおり接種できない場合、2回目の接種は1回目接種後1月以上の感覚をおいて行った後、3回目の接種は1回目接種後5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて行うことができます。
(2)4価ワクチン:ガーダシルを接種する場合(3回接種)
- 1回目の接種をしてから2月の間隔をおいて2回目を接種し、1回目の接種から6月の間隔をおいて3回目を接種。
- ただし、やむを得ず上記のとおり接種できない場合、2回目の接種は1回目接種後1月以上の間隔、3回目の接種は2回目の接種から3月以上の間隔で接種を行うことができます。
(3)9価ワクチン:シルガードを接種する場合(2回もしくは3回接種)
- 令和5年度より定期接種が可能となりました。
- 1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、6月の間隔をおいて2回接種します。ただし、やむを得ず上記のとおり接種できない場合、5月以上の間隔をおいて2回行う。
- 1回目の接種を15歳以上で受ける場合、2月の間隔をおいて2回、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回接種します。ただし、やむを得ず上記のとおり接種できない場合、1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。
接種場所
- 予防接種の種類・接種医療機関(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
当日持参するもの
- 通知書(予診票)記入を忘れずに
- 母子健康手帳
どちらか忘れた場合は接種できませんのでご注意ください。
また予診票は必ず令和5年4月以降発行のものを御使用ください。
予診票を紛失された方は再発行しますので、本市までお問い合わせください。
任意接種済みの皆様へ
積極的な勧奨の差し控えにより、予防接種法に規定する予防接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日に生まれた女性であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた方に対して、費用助成を行います。
対象者
- 平成9年4月2日~平成17年4月1日に生まれた女性
- 令和4年4月1日時点で垂水市に住所がある方
- 定期接種の対象時期(小学6年生~高校1年生年度末まで)以外で子宮頸がん予防ワクチンを任意接種(全額自己負担)で接種した方
- 令和4年4月以降に接種(キャッチアップ接種)を受けていないこと
助成内容
最大3回接種分/1回上限15,727円
申請期限
令和7年3月31日まで
申請書類
- 申請書(PDF:125KB)
- 医療機関領収書の写し
- 本人確認書類
- 接種記録が確認できる母子手帳等
- 任意予防接種償還払い申請用証明書(PDF:70KB)(接種記録が確認できる母子手帳等が手元にない場合)
任意予防接種償還払い申請用証明書を接種された医療機関にて記入を依頼してください。 - 振込口座の写し
医療機関の皆様へお願い
対象者・接種可能期間・ワクチンの種類・接種回数について
償還払い(任意接種償還払い申請用証明書発行)制度へのご協力について
本市では令和4年3月31日までに任意接種(全額自己負担)された方への、救済措置として、その費用を助成する「償還払い」制度を行います。
この制度では対象者本人が、本市に申請を行いますが、接種証明書に関する書類が必要になります。
母子健康手帳や予防接種証明書が準備できない場合に、本人から医療機関に対し、「任意接種償還払い申請用証明書(PDF:70KB)」の発行をお願いすることがあります。
その際はご対応お願いいたします。
その他
予診票の有効性の疑義が生じた場合や、ワクチン接種に関してご不明な点がある際は、必ず本市までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
- ヒブワクチン
- 小児用肺炎球菌ワクチン
- 四種混合ワクチン
- 二種混合ワクチン
- BCGワクチン
- 不活化ポリオワクチン
- 麻しん風しん混合(MR)ワクチン
- 日本脳炎ワクチン
- 子宮頸がん予防ワクチン
- 水痘(水ぼうそう)ワクチン
- 成人用肺炎球菌ワクチン
- 風しんの追加的対策
- 予防接種の種類・接種医療機関
- ロタウイルスワクチン
- B型肝炎ウイルス
- 令和6年度新型コロナワクチン定期接種助成事業
- 任意予防接種助成
- おたふくかぜワクチン
- 予防接種健康被害救済制度
- 令和6年度インフルエンザ予防接種助成事業
- 子ども予防接種週間
- 妊婦等風しんワクチン助成
- 五種混合ワクチン
- 帯状疱疹ワクチン助成
- 子どもの予防接種における委任状の提出について