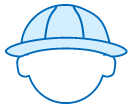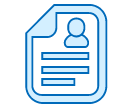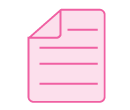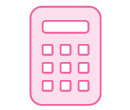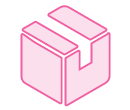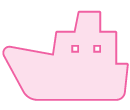更新日:2024年6月10日
ここから本文です。
全国家計構造調査
令和6年全国家計構造調査にご協力をお願いします。
「全国家計構造調査」は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする調査です。
この調査は、昭和34年(1959年)に「全国消費実態調査」としてスタートし5年毎に実施されてきましたが、前回の令和元年(2019年)調査に全面見直しされて、「全国家計構造調査」となりました。
今回の調査は、全国消費実態調査から通算すると14回目の調査となります。
調査の期間
令和6年(2024年)10月及び11月の2か月間実施します。
調査対象
全国から無作為に選定した約90,000世帯が対象です。
調査内容
【世帯及び世帯員に関する事項】
世帯構成、世帯員の就業・教育状況、現住居の状況、現住居以外の住宅・宅地の保有状況など
【家計収支に関する事項】
自動引落しによる支払、口座等への入金(給与・年金等)、日々の収入と支出など
【所得及び家計資産・負債に関する事項】
年間収入、預貯金などの金融資産、借入金、企業年金掛金・固定資産税など
調査方法
調査員が調査対象世帯に調査票を配布することにより行います。調査票の提出は、次のいずれかの方法を世帯が選択することができます。
- インターネット回答(オンライン回答)※推奨
- 調査員に提出
- 郵送により提出(「簡易調査」のみ)
回答の際は、便利なインターネット回答をご利用ください。
結果の利用
国や地方公共団体において、国民年金・厚生年金の年金額の検討、介護保険料の算定基準の検討、生活保護の扶助額基準の検討、税制改正に伴う政策効果の予測、所得格差・資産格差の現状把握、高齢者の金融資産保有状況の把握など、重要な政策に使われます。
個人情報は厳重に保護されます
この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく「基幹統計調査」(基幹統計「全国家計構造統計」を作成するための調査)で、国が実施する統計調査のうち特に重要な調査です。
統計調査員には、調査の結果知り得た秘密は漏らしてはならない守秘義務が規定されており(統計法第41条)、これに違反した者に対する罰則が定められています。(統計法第57条)
また、全国家計構造調査の情報は、総務省統計局のホームページでもご覧いただけます。
関連リンク
- 総務省統計局ホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンクします)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください